・高配当投資に興味または既に投資をしていて、「配当控除制度」について知りたい方
・実際に配当金の税率をどれくらい減らすことができるのかを知りたい方
・どんな人がこの配当控除制度を利用できるのかを知りたい方

日本の高配当投資は盛り上がっていますね。毎月お金が企業からもらえるなんて夢の不労所得生活!! でも、配当金にも20.315%もの税金がかかるとなると少しでも税金って減らせないんだろうかぁ。。。せっかくもらえるお金も20%も国に税金として徴収されるなんてつらいなぁ。


・高配当投資に興味または既に投資をしていて、「配当控除制度」について知りたい方
・実際に配当金の税率をどれくらい減らすことができるのかを知りたい方
・どんな人がこの配当控除制度を利用できるのかを知りたい方

日本の高配当投資は盛り上がっていますね。毎月お金が企業からもらえるなんて夢の不労所得生活!! でも、配当金にも20.315%もの税金がかかるとなると少しでも税金って減らせないんだろうかぁ。。。せっかくもらえるお金も20%も国に税金として徴収されるなんてつらいなぁ。

夢の不労所得生活は皆のあこがれですね。
さて、日本株の売却益、配当金に関しては特定口座であれば、両方ともに強制的に20.315%は税金として徴収されます。ただし!配当金に関しては実は「配当控除」という制度があり、これを申請することで税率を軽減することが可能なんです。今回はこの配当控除という制度を紹介するとともにどのようにすると税金を取り戻せるのかを解説します。

配当金とは、投資している会社の業績に応じて年に1,2回受け取ることができる金銭のこと。
所得税法上では「配当所得」にあたる。
基本的には、配当所得=収入金額(税金を引く前の額)になります。※借入して購入した株は別
特定口座(源泉徴収あり)の場合は配当金=配当所得×20.315%(所得税15.315%+住民税5%)
配当金については、原則確定申告の必要はありません。
理由は、配当金として支払われるときに一定の所得税と住民税が源泉徴収されるているため。

そもそも、配当金の確定申告の方法は3種類あります。
1.申告不要制度(確定申告をしない)
申告不要制度とは、名前の通り、配当金について「確定申告しない」とする制度。
多くの人が証券会社の口座を「特定口座(源泉徴収有)」としている理由でもある。
2.総合課税で確定申告
総合課税とは?・・・1年間のその人が得た所得を合計して課税の対象とする計算する方法。 一般の給与に含める形での課税方式です。
⇒「配当控除制度」が利用でき、源泉徴収された税金が一定額の税金を控除(配当控除)でき、還付される可能性があります。
3.分離課税で確定申告
分離課税とは?・・・特定の所得については他の所得と合計しないで、その所得だけに独自の税率をかけて所得税の計算をする制度です。例えば、日本株の売却益や配当金は特定口座(源泉徴収あり)の場合は一律20.315%の税率(所得税15.315%、地方税5%)をかけて所得税を算出しています。
| 総合課税 | 分離課税 |
|---|---|
| 対象となるすべての所得を合計し、その 合計金額が課税対象となる。 | 所得の種類ごとに個別に課税される |
| 給与所得 事業所得 配当所得 不動産所得 山林所得 一時所得 雑所得 | 株式等の譲渡所得 配当所得 退職所得 山林所得 土地建物等の譲渡による譲渡所得 所定の利子所得及び一定の先物取引 による雑所得等 |

配当控除制度とは、国内株式の配当等について総合課税で確定申告した場合に適用される算出税額から一定の金額が控除される制度のことです。
なぜこの制度があるのか?⇒ズバリ、法人税と所得税で二重課税になるから!
企業は利益に対して法人税が課されているので配当は法人税が課された後の利益から株主に支払われています。この配当に対してさらに所得税がかかるとなると二重課税になってしまうため、これを排除するために設けられた制度が配当控除です。
では外国株式の配当金にかかる部分の制度は?
以前、「米国株式で高配当投資をするなら、必ず「外国税額控除」で10%の税金を取り戻そう!」で紹介した記事がありますのでぜひこちらも合わせてお読みください。


日本の高配当株式投資は、日本の中での法人税との兼ね合いで一部が控除されるということは、配当を貰う側としては税金面ではお得ですね。こちらは外国株の高配当に関しては、控除されないため税金面で見れば不利な点です。(成長性の面ではまた違った見方になるかと思います)
税金面でいうと基本的には
日本の高配当株式投資の税金 < 外国の高配当株式投資の税金
ということが言えるでしょう。
ただし、日本の高配当株式投資の税金が安くなるのは、所得が900万以下の場合はお得という条件付きですので、その点については次のお話で詳しく解説したいと思います。

では、配当金に対する税金の控除でどんな人がどれくらいの税金は戻ってくるものなのでしょうか?
実は、免除される配当控除の税率というものが存在します。
| 課税総所得金額 (配当所得を含む) | 所得税 配当控除税率 | 住民税 配当控除税率 |
| 1000万以下 | 10% | 2.8% |
| 1000万を超えた部分 | 5% | 1.4% |
たとえば、配当所得が10万円のケースでは、1万円を所得税額から、2,800円を住民税額から控除することができます。
次にどんな人であれば、総合課税で配当控除を申請するとお得になるのでしょうか?
所得税⇒課税所得金額が900万円以下であれば、総合課税が有利!
住民税⇒申告不要
課税所得金額が900万円以下であれば、上場株式等の配当については所得税で総合課税を、住民税で申告不要を選択すれば、最も有利な結果になります。
配当金の所得税に関しては、10%(※基本的に1000万以下の方)の税金が免除されます。

配当控除申請すべき人は、課税所得900万以下であると総合課税が有利であります。
以下は、確定申告しない場合(源泉徴収税率)と、総合課税で確定申告した場合を比較した表になります。
■確定申告しない場合(源泉徴収税率)VS 総合課税で確定申告した場合
配当金に対する実質税率は?
| 課税される所得金額 (配当含む) | 源泉徴収税率 (確定申告なし) | 基本 所得税率 | 総合課税による 免除される 配当控除税率 (割引税率) | 配当金に 対する 実質税率 | 総合課税が 有利〇 不利× |
|---|---|---|---|---|---|
| 195万円以下 | 15.315% (一律固定) | 5% | 10% | 0% ⇒15.315%お得! | ◎ |
| 195万円 を超え 330万円以下 | 15.315% (一律固定) | 10% | 10% | 0% ⇒15.315%お得 | ◎ |
| 330万円 を超え、 695万円以下 | 15.315% (一律固定) | 20% | 10% | 10% ⇒5.315%お得 | 〇 |
| 695万円を超え、 900万円以下 | 15.315% (一律固定) | 23% | 10% | 13% ⇒2.315%お得 | 〇 |
| 900万円 を超え、 1000万円以下 | 15.315% (一律固定) | 33% | 10% | 23% | × |
| 1000万を超え、1800万円以下 | 15.315% (一律固定) | 33% | 5% | 28% | × |
| 1800万円を超え、 4000万円以下 | 15.315% (一律固定) | 40% | 5% | 35% | × |
| 4000万円 以上 | 15.315% (一律固定) | 45% | 5% | 40% | × |
次に、所得に対する配当金の実質税率がお得な人々をまとめました。
・所得金額が195万円以下 ⇒配当金に対する実質税率は0%!(15.315%お得!)
・所得金額が195万円 を超え 330万円以下 ⇒配当金に対する実質税率は0%!(15.315%お得!)
・所得金額が330万円 を超え、 695万円以下 ⇒配当金に対する実質税率は10%!(5.315%お得!)
・所得金額が695万円を超え、 900万円以下 ⇒配当金に対する実質税率は13%!(2.315%お得!)
では、所得900万円以下(※所得は年収から控除金額を引いた額)の人はどれくらいいるのかというと、全国民の83%にもなります。
■所得金額階級別にみた世帯数の相対度数分布(平成21年厚生労働省調べ)
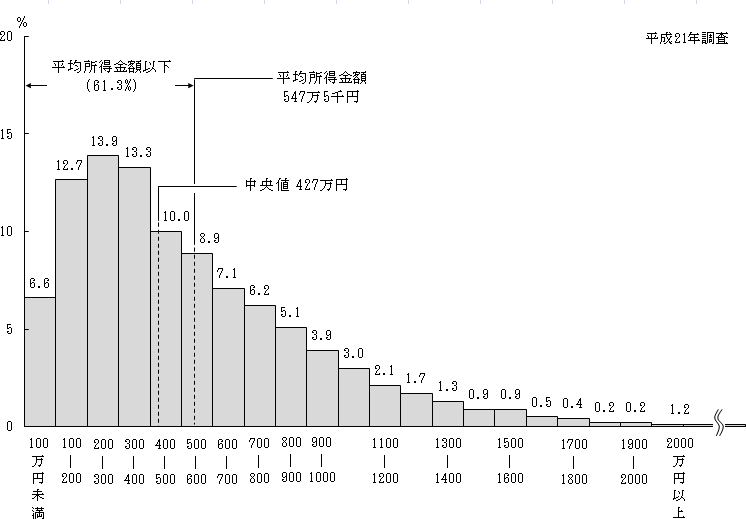

住民税については、所得の多い少ないに関わらず、確定申告すると不利になります。
以下は、確定申告しない場合(源泉徴収税率)と、総合課税で確定申告した場合を比較した表になります。
■確定申告しない場合(源泉徴収税率)VS 総合課税で確定申告した場合
配当金に対する実質税率は?
| 課税所得金額 | 源泉徴収税率 (確定申告なし) | 基本的な 住民税率 | 総合課税による 免除される 配当控除税率 (割引税率) | 配当金に 対する 実質税率 | 総合課税が 有利〇 不利× |
| 1000万以下 | 5%(一律固定) | 10% | 2.8% | 7.2% | × |
| 1000万超 | 5%(一律固定) | 10% | 1.4% | 8.6% | × |
次に、住民税に対しての配当金の実質税率がお得な人々をまとめました。
配当金にかかる住民税に関しては
所得に関わらず、確定申告はしないで、源泉徴収税率 5%(一律固定)を選ぶべきである
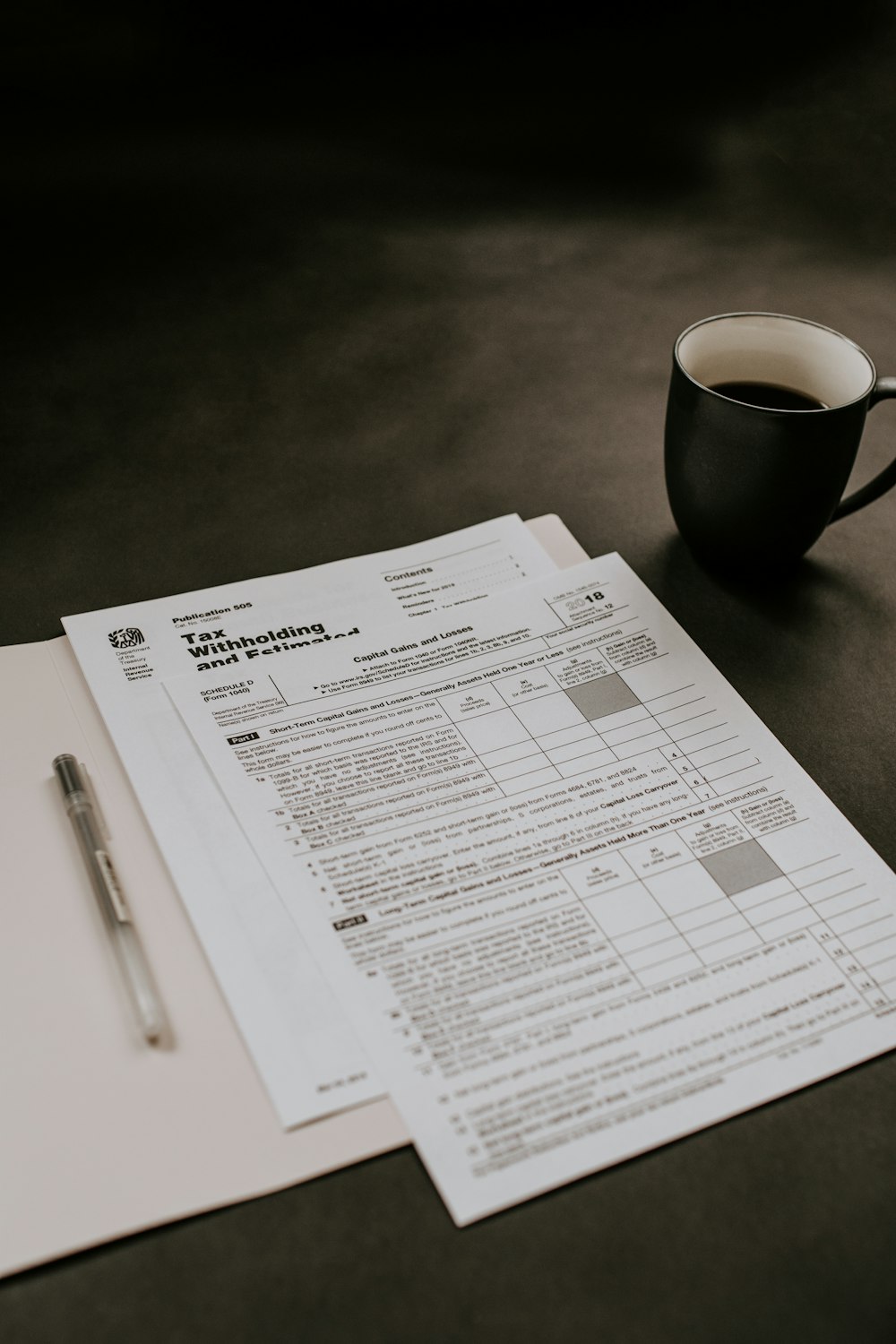
所得税と住民税はそれぞれ別々の申告方法を選択すべきである。
所得900万以下の人であって配当金に対する税金を安くしたいのであれば、
・所得税は総合課税で確定申告すべき
・住民税は申告不要で区や市で申請(届け出)を出すべき(申告不要は手続きなしではなく、申請(届け出)は必要です!)
であります。
住民税に関しては、「分離課税」という手段もあるのですが、こちらに関しては国民健康保険料や介護保険料の増加を避けるためです。実は社会保障に係る負担の算定は住民税の所得額が基礎になっていまる。配当所得を総合OR分離のどちらかで申告すると社会保険関連の負担も増えますので申告不要にすれば影響はありません。
所得税と住民税を別々に申告する手順は?
手順1. 所得税を総合課税で確定申告する
※以前は確定申告時に配当金について総合課税を選択するとそのまま住民税も適用されていたが、地方税法が改正後は、別々にできるようになった。
手順2.住民税を申告不要とする申請をする
確定申告とは別で、各自治体の窓口へ住民税の納税通知書が届くまで(6月頃)に「住民税申告書」の提出が必要です。申告の際に使用する書式は自治体によって違うためHP等の確認を実施しましょう。

住民税に関しても申告不要でも、自治体(市や区)に申請は必要ですので注意してください!ここは誤解されてしまうと、そのまま住民税は5%適用されなくなるので逆に増税になり、損をすることになるので気を付けてください。

配当株投資していて、所得900万円以下の人は、確定申告することで、
所得330万以下の人は、配当金に対する税金が15.315%割引されてお得!
所得330万円を超え、 695万円以下の人は、配当金に対する税金が5.315%割引されてお得!
所得695万円を超え、 900万円以下の人は、配当金に対する税金が2.315%割引されてお得!
例えば、仮に1000万円の日本の高配当株をもっていて、利回り5%とすると、年間税込み50万の配当金額を貰っている方は
所得330万円を超え、 695万円以下の方であれば、⇒約2.6万円が還付されます。
所得695万円を超え、 900万円以下の方であれば、⇒約1.1万円が還付されます。
さて、かなり長く配当控除について話をしてきましたが、今までの内容をここでまとめたいと思います。
1.配当金とは、投資している会社の業績に応じて年に1,2回受け取ることができる金銭のこと。特定口座(源泉徴収あり)の場合は配当金=配当所得×20.315%(所得税15.315%+住民税5%)になる。
2.配当金の確定申告の方法は3種類。申告不要制度(確定申告をしない)、総合課税で確定申告する、分離課税で確定申告するの3つになる。
3.配当控除制度とは、国内株式の配当等について総合課税で確定申告した場合に適用される算出税額から一定の金額が控除される制度のことです。
4.課税所得金額が900万円以下であれば、上場株式等の配当については所得税で総合課税を、住民税で申告不要を選択すれば、最も有利な結果になります。配当金の所得税に関しては、10%(※基本的に1000万以下の方)の税金が免除されます。
5.課税所得900万以下であると、総合課税で申告すると配当金の2.315% ~15.315%お得になる(この税率分が還付される)
6.配当金にかかる住民税に関しては所得に関わらず、確定申告はしないで、源泉徴収税率 5%(一律固定)を選ぶべきである
7.所得900万以下の人であって配当金に対する税金を安くしたいのであれば、所得税は総合課税で確定申告すべき、住民税は申告不要で区や市で申請(届け出)を出すべき(申告不要は手続きなしではなく、申請(届け出)は必要です!)

さて、この配当控除申請を用いることはもちろんほぼすべての人がやるべきだとは思いますが、特に 高額(1000万以上)で高配当株式投資をやっている人はその効果が高いので必ずやるべきだとは思います。ただ、高額で高配当投資をやっている方は基本的に所得が高くなりやすいと思いますので、「所得900万以下である」ということは気を付けなければならない重要な条件にはなるでしょう。
確定申告は サラリーマンであるとほとんどの方が住宅ローンの時以外は実施しない方も多いかとは思います。しかし、いつかは誰もが退職し、引退する時(アーリーリタイヤも含む)が来るわけで、自分で稼いだお金に対する税金を理解しておくことはどんなに小さな額でも申請して取り戻すという習慣は身につけたいですね。
サラリーマンであることは、一定の安心を得られる手段ですが、同時に国からは税金をしっかりと取られるターゲットにはなりますので、こうした節税の手段や方法は知っておきたいところです。
